未経験から漁師への転職を考えているものの、何から始めれば良いかわからないという人も、多いのではないでしょうか?
この記事では漁師になるための基本情報から具体的なステップ、求人やキャリアアップの情報まで、できるだけ分かりやすく解説しています。
漁師という職業の魅力・素晴らしさ・大変さを理解することで、将来像が描きやすくなると思います!
■この記事で得られる主な内容
- 漁師としての仕事内容や就業スタイル:日常の業務や独立型、雇用型の就業スタイルの違いを解説
- 漁師になるための具体的な方法:必要な資格やステップ、教育機関について詳しく紹介
- 漁師への転職とキャリアアップ:脱サラして漁師になる際の注意点や、漁師としてのキャリアアップ方法を提供
- 漁師への適正:漁師に向いている人・不向きな人が良くわかる
読了後、あなたは漁師としての新たなキャリアをスタートさせるための具体的な行動を起こせるようになります。
この機会に、漁師という職業の全体像を理解し、次のステップへと進んでみませんか?
まず初めに 漁師とは?
漁師(りょうし)とは、 海・川・湖などで魚や貝、海藻などを捕獲・採取して生計を立てている人々を指します。
もっと簡単に言うと、「魚介類・海産物を集める仕事をしている人」が、漁師に該当します。
漁師の職場は、主に次の2か所です。
- 主に 海(沿岸や沖合)
- または 川や湖(内陸)
船に乗って沖に出る人もいれば、浜辺や川岸から網を使って漁をする人もいます。
漁師の仕事内容や時間
前述の通りですが、漁師の仕事は魚や他の海産物を捕まえて、市場に流通させる職業です。
漁師の作業は早朝から始まり、時には夜明け前に海に出ることもあります。
仕事の時間は、漁場の位置や狙う魚種によって異なりますが、一般的には長時間労働になりがちな仕事です。
また、天候によっては出漁できない日もあり、その場合は網の修理や漁具の手入れなど、他の作業を行います。
漁師の就業スタイル(雇用型と独立型)
漁師には大きく分けて二つの就業スタイルがあります。一つは雇用型で、漁業会社や漁船の経営者に雇われて働くスタイルです。
雇用型とは従業員として賃金を得る就業方式で、一般的だと言えます。
もう一つは独立型で、自分自身で漁船を持ち独立して漁業を行う方法です。
雇用型の場合は安定した収入が見込める一方で、独立型では多額の初期投資が必要になります。
また、独立型漁師は自分で漁場を選び販売先を確保する必要があり、事業主としてのスキルも求められます。
ただし危険を犯して独立する分、雇用型以上に大きな収入を得られる可能性もあるのが特徴です。
漁師に向いている人
漁師に向いている人は、以下の通りです。
- 体力があり、筋力が高い人
- 暑さや寒さが苦にならない人
- 船酔いに強い人
- 協調性があり、意思疎通ができる人
- 視力が良い人
それでは、順次解説します。
体力があり、筋力が高い人

まず、漁師は肉体労働です。基本的に、体力や筋力はとても重要な要素です。
立ち仕事ですし、重たい物を扱う機会が多い職種です。
・漁網
・ロープ
・カゴ
・エンジン部品
こうした重量物を扱う職種なので、体力や筋力が低い人では、かなり大変だと言えます。
ただし、漁法によっては筋力をそれほど必要としない漁業も存在しますので、必ずしも体力・筋力が必要という訳ではありません。
・自動巻き上げ機などの機械化
・分業化
・養殖産業などの、力仕事が少ない漁業形態
上記のような職場も存在しますので、ご自身の体力・筋力と相談して決めましょう。
暑さや寒さが苦にならない人

漁師は屋外で活動します。それこそ、時期によっては猛暑日・厳寒期でも活動します。
気温の急激な変化などについていける人であれば問題ありませんが、暑さ・寒さが苦手な人は大変です。
船酔いに強い人

漁師は基本的に、船の上で活動します。船は当然ながら揺れますので、酔いやすい人には辛い仕事です。
これは個人差が非常に大きく、船酔いしやすいかどうかは、ある程度先天的に決まっています。
脳機能(三半規管)や体質、体調、心理状態などに左右されます。
乗り物・船酔いに耐性がない人では、かなり厳しい仕事と言えるでしょう。
協調性があり、意思疎通ができる人

漁師は基本、分業作業を行います。他の漁師(搭乗員)たちと連携して作業します。
意思疎通(他者の話を聞いて、必要ならば自己主張を行う)がしっかりできないと、成果は出づらいと言えます。
経験が少ないときは、先輩・上司の指示に素直に従って作業をしなければなりません。また、独立して漁師を目指す方は、販売先(取引相手)の開拓なども必要です。
このときも、しっかりと意思疎通する力(コミュニケーション能力)が大切になってきます。
視力が良い人
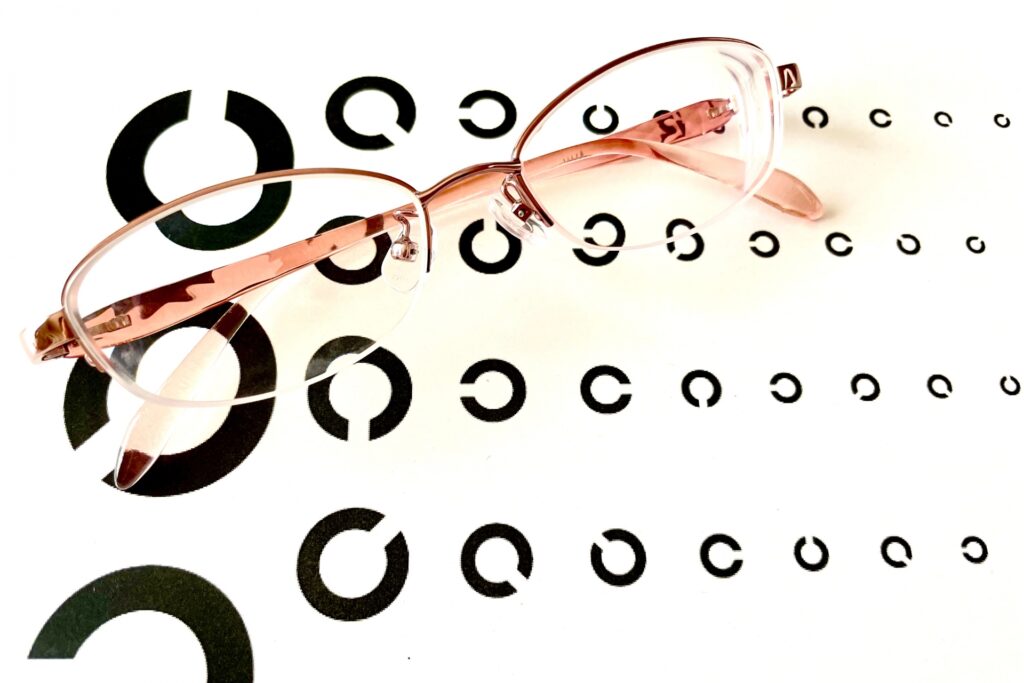
これは主に漁獲型(船上で魚介類を採集する漁師)が対象です。漁獲型漁師には厳密な視力基準は存在しません。
ただし、海上では魚などの動きを目視したり、天候・波の変化などを察知しなければなりません。視力が高い方が絶対に良いのは、簡単に想像できると思います。
その他にも、以下のような場面で視力はとても大切になります。
・他船との位置取りを把握する
・障害物などが無いかを確認する
・夜間作業のときでも、正確な作業ができる
視力が低い(メガネ・コンタクトで矯正しても目が悪い)人は、まず適正が無いと言えます。
ただし、養殖業などであれば、高い視力は必要ありません。
生け簀(いけす)や水槽管理、餌を与える・健康を管理するといった作業が主要業務だからです。
また、小型船舶の操縦士として活動する為には、必ず視力基準が設定されています。
例えば、次の通りです。
| 視力基準(国土交通省) |
| 両目で0.7以上(メガネ・コンタクト使用可能) |
| 片目が見えない場合・・・反対の目で0.7以上+視野制限無し |
小型船舶操縦士の免許を取得する場合は、矯正視力で0.7以上を確保できれば問題ありません。
それなので、漁獲型漁師を目指さないのであれば、目が悪い人でも十分に活躍する機会はあります!
具体的に 漁師になる方法
漁師になるためのステップ
未経験者が漁師になるには、以下の段階を経て漁師を目指すと良いでしょう。
- 関連知識の習得 漁業に関する基本的な知識を学びます。これには、魚種の識別・海洋学・気象学の基礎が含まれる
- 実地訓練 漁師養成学校や漁業協同組合が提供する研修プログラムに参加し、実際に海での作業技術を習得
- 資格の取得 漁船を運航するために必要な小型船舶操縦士の資格など、専門的な資格を取得
- 経験の積み重ね 経験豊富な漁師のもとで働き、実務経験を積みます。これにより、漁業のノウハウを身につける
漁師に必要な資格など
漁師になるためには、原則として学歴は必要ありません。
ごく一般的な漁業活動に従事するのであれば、資格などは不要で活動できます。
ただし、一部の業務を行うためには専門資格が必要です。独立志望の方は特に注意しなければなりません。
資格その1 海上特殊無線技士免許
まずは、海上特殊無線技士免許です。
これは、漁船の無線機器を使用するために必要な免許(資格)です。
例えば、漁船同士で連絡を行う際に無線を使用します。そのほかにも、海上漁船と陸地での連絡などにも使われます。
1級や2級など等級が存在していて、等級が上昇するに伴い、担当できる業務内容も増やせます。
| 等級 | 権限の大小 |
| 1級 | 船舶(※)などで無線通信を行う為には必須。国際航海まで対応できる (※20トンを超える、大型の商業用海上船) |
| 2級 | 国内航海で無線通信が可能。国際航海はできない |
| 3級 | 沿岸海域での小型漁船、またはプレジャーボート(非営利目的の小型船)の無線電話のみ操作可能 |
試験を実施している団体
- 総務省の認可を受けた「公益財団法人 日本無線協会」
資格その2 小型船舶操縦士
船舶を操縦する為に必要な免許です。こちらも等級により、操縦できる船の種類が変わってきます。
1級小型船舶操縦士であれば、20トン未満の商業用船などを運転できます。
船の大きさや活動区域によって、必要な等級は異なります。
(1級、2級、2級湖川限定、特殊の合計4種類)
ちなみに、20トン以上の業務用大型船舶を操縦するためには、「海技士免許」などが必要です。
| 等級 | 権限の大小 |
| 1級小型船舶操縦士 | 20トン未満の船舶を操縦可能。基本的には、すべての水域で活動可能 ただし、沿岸部から80海里(約150km)より遠い海域で活動する場合は、6級海技士(機関士)を同乗させる必要有り |
| 2級小型船舶操縦士 | 海岸から5海里(約9km)以内の水域で、活動可能 ※18歳未満の場合、5トン未満の小型船のみ操縦可能 |
| 2級小型船舶操縦士(湖川限定) | 湖や川だけで活動可能。 総重量5トン未満、エンジン出力15KW未満の船に限定される |
| 特殊小型船舶操縦士免許 | 湖岸または海岸から2海里(約3.7km)まで活動可能。運転できるのは、水上オートバイのみ |
試験を実施している団体
- 管轄→国土交通省
- 試験や講習→「一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会(JMLA)」が実施している
資格その3 海技士免許
海技士免許は、商船・貨物船・旅客船などの大型船で、船長や機関長として働くために必要な国家資格です。
等級と分野に区分されており、資格ごとに実行可能業務が異なります。
| 分野 | 内容(担当可能な範囲) |
| 航海 | 船の運転・航路計画・航海の安全管理を担当 |
| 機関 | エンジン・発電機などの動力設備の管理を担当 |
| 通信 | 無線通信の運用・設備の管理を担当(大型船など) |
| 電子通信 | 高度な通信・レーダー・航法機器の運用を担当(特殊) |
「等級」
| 等級 | 対応する船舶、活動可能範囲 |
| 1級 | 国際航海が可能。20トン以上の大型船舶まで従事可能(最上位) |
| 2級 | 20トン未満の外航船(国際的な航海)にまで対応 |
| 3級 | 国内漁業を行うことが可能。国際航海は不可(沿岸部・内航船など) |
| 4~6級 | 小規模な船、限定された区域のみ可能。地方漁業向けが多い |
簡単にまとめると、次の通りです。
- 上の等級になるほど大きな船・広い航行区域で働ける
- 分野によって担当する仕事が違う
- 航海 → 船を動かす
- 機関 → エンジン・動力炉を動かす
- 通信 → 無線を使用して交信を行う
- 電子通信 → 高度な機器やレーダーなどを管理する
試験を実施している組織・・・地方運輸局
管轄・・・国土交通省
補足 海技士と航海士・機関士の違い
よくある疑問に、「海技士と航海士・機関士は何が違うのか?」という質問があります。
結論から言うと、「航海士・通信士・機関士=海技士」です。厳密には海技士の一部門が、航海士や機関士と呼ばれているだけです。
分かりやすく説明すると、下記の通りです。
- 1 海技士(通信士)
- 2 海技士(機関士)
- 3 海技士(航海士)
3は海技士ですが、航海担当(航海士)です。航海計画を立てたり、船の操縦などの業務を行います。
2もまた海技士です。しかし、担当は、船の動力炉(機関部)を管理しています。
1も同じです。海技士ですが、無線・レーダーなどを使用した通信を主に担当しています。
| 担当部門 | 必要な免許(一例) |
| 船長 | 海技士(航海)1級 |
| 航海士(フェリー) | 海技士(航海)3級など |
| 機関長 | 海技士(機関)1級 または 2級 |
| 機関士(国内航海) | 海技士(機関)3級など |
| 無線長 | 海技士(通信)1級 |
| レーダー・電子機器担当 | 海技士(電子通信)1級 |
紛らわしいですが、表にすると簡単にお分かり頂けると思います。皆さん、海技士ですよね(笑)?
例えば司法試験では、合格者は裁判官・検察官・弁護士などに分かれます。しかし、通称(俗称)は法律家と呼ばれるのが一般的です。
これと全く同じです。
法律家と呼ばれる仕事ではありますが、法曹三者の仕事内容は全く違います。
- 裁判官→民事または刑事裁判で、合理的な正しい最終判断を下す
- 検察官→被疑者を刑事裁判にかける手続きを行い、有罪を立証する
- 弁護士→依頼人の代理人として活動し、民事や刑事裁判などを代行する(刑事裁判では弁護人として活動)
紛らわしいかもしれませんが、上の図を見れば、簡単に分かると思います。
教育機関や全漁連を、フル活用する

漁師になるためには、専門的な知識と技術が必要です。日本では、多くの公共機関や私立学校が漁業教育を実施しています。
これらの教育機関では、海洋生物学・船舶操作・海洋安全・気象学など、漁業に必要な幅広い知識を学習可能です。
例えば、「全国漁業協同組合連合会」(全漁連)は、漁業を志す人々を対象にした研修制度を多数実施しています。
また、地方によっては地元の漁業協同組合が独自の訓練プログラムを提供しており、漁師としての基本スキルだけでなく、地域特有の漁法についても学ぶことができます。
教育プログラムは通常、基礎教育から実践的なトレーニングまで存在しており、未経験者であっても安心です。
入門コースでは、海洋生態系の基礎知識や漁業法規などが教えられ、上級コースでは実際に船を操作して海上での作業技術を習得します。
- 日本海洋大学 – 漁業科学部が設けられており、漁業技術だけでなく、海洋環境についても学習可能です
- 全国漁業協同組合連合会 – 短期集中講座やオンラインでのセミナーも開催しており、働きながら学べます
- 地方自治体が運営する漁業学校 – 地元の漁業に特化したカリキュラムを提供しています
漁業セミナーやフェアは、漁師を目指す人々にとって貴重な情報源です。
これらのイベントでは、漁業技術の実演・最新の漁業機器の展示・業界の専門家による講演などが行われ、参加者は直接業界の現状やトレンドを学べます。
例として、「全国漁業フェア」は年に一度、複数の都市で開催され、漁業関連の最新技術や商品が展示・公開されています。
また、地域ごとに特化した小規模なセミナーも多く、特定の漁法や魚種に焦点を当てた実践的な知識を教えていることも多いです。
- 全国漁業フェア:新技術の展示、漁業機器のデモンストレーション、専門家によるパネルディスカッション
- 地方漁業セミナー:地元の漁法や市場の特性に合わせた専門的な知識と技術の提供
- オンラインウェビナー:アクセスしやすい形式で、最新の漁業情報や技術が共有される
これらの教育機関や組織団体・イベントを活用し、効率的に漁師としてのスキルを身につけましょう。
そうすれば、未経験からでも漁師になるのは夢ではありません。
漁師という職業はただ漁をするだけでなく、海洋環境の保護者としての役割も果たす重要な仕事です。
ですから、適切な教育と情報がその成功の鍵となります。
漁師(特に漁獲漁)への転職を考えている場合、まずは適正を考えたほうが良いでしょう。基本的には肉体労働であり、体力が必要です。
脱サラして漁師になる際には、体力と気力・資金面の準備が必要です。
また漁師としての生活は、一般的なオフィスワークとは異なります。不規則な労働時間が常であり、季節によって働く時間や量が大きく変動します。
漁師の平均年収
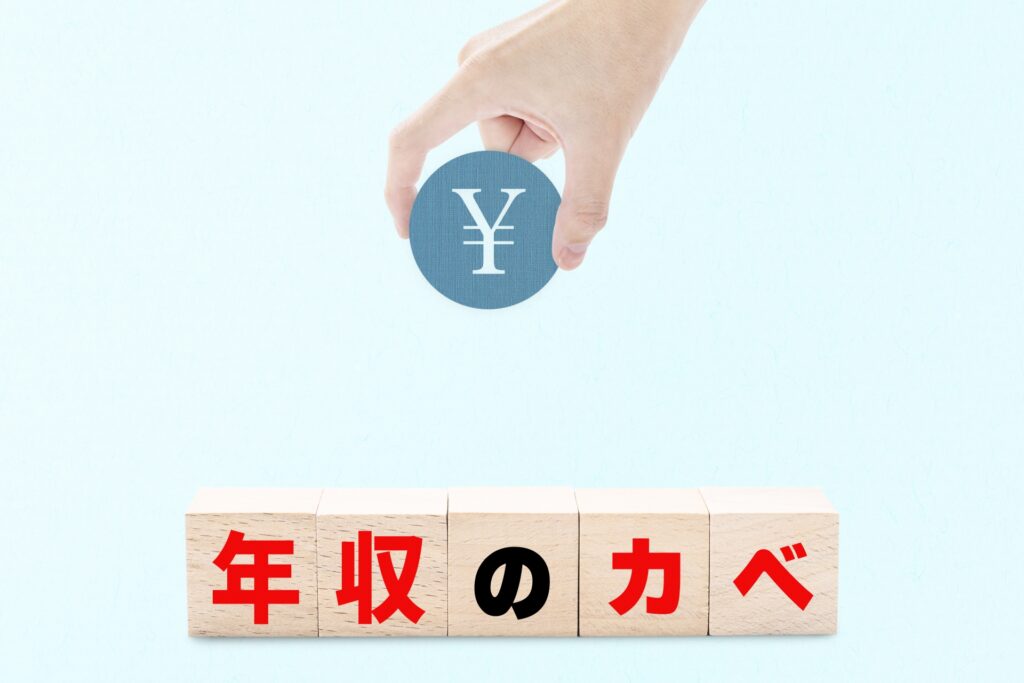
日本の漁師の平均年収は地域や漁法・経験によって異なりますが、公的な統計によると約300万円から650万円程度です。
しかし、独立して船を持つ場合や、特定の魚種を専門とする高収入を得ている漁師もいます。
特に高収入なのは、遠洋漁業従事者(大型船で海外での漁業を行う漁業)です。
遠洋漁業従事者の平均年収は、約650万円と、かなりの高収入を得ています。中には800万円~1500万円もの年収を得ている漁師もいらっしゃるので、驚きですね。
ただし、遠洋漁業は1年のうち約8~10か月は船上(海の上)で生活しなければなりません。
相当に過酷なので、適正が無ければ不可能だと言えます。
まずは小さく動いてみる
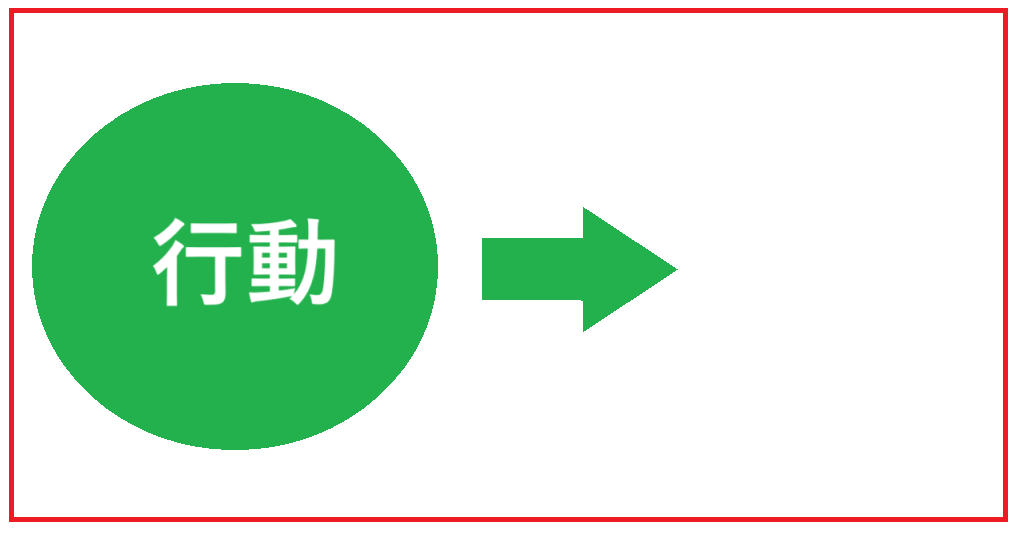
ここまで書くと、「漁師になるのは大変すぎるのか。どうしよう・・・」と考えてしまう方も多いでしょう。
しかし、漁師を目指したいという思い・目的があるならば、小さくとも動き出す方が良いかもしれません。
具体的には、以下のような方法を検討すれば良いでしょう。
- 体験入漁: 実際に漁師としての仕事を体験してみた方が無難。多くの漁港では短期間の体験入漁が可能
- 資金計画の立て方: 独立する場合は、ほとんどの場合初期投資が必要(例えば船や漁具の購入)。資金計画をしっかりと立ててから独立するべき
- 地域の漁協との関係構築: 地元の漁業協同組合と良好な関係を構築できれば、情報やサポートを得やすくなる
漁業求人や、情報サイトを探す

漁師としてのキャリアをスタートさせるためには、適切な求人情報の収集が不可欠です。漁業求人は、地方自治体や漁業協同組合・専門の求人サイトで確認できます。
特に地元の漁協では、地域に根差した求人情報が豊富にあります。
漁師としてのスキルや経験を積むことにより、キャリアアップの道も開かれます。例えば大型船の船長や、高価値の魚介類を扱う専門の漁師になることが可能です。
また、自ら魚市場で魚を売り込む能力を身に付けられれば、収入を大幅に増やせる可能性も高まります。
- 専門技術の習得: 特定の漁法や魚種に特化すれば、市場での需要に応えられる専門家になれる可能性が高い
- 人脈(ネットワーク)の構築: 他の漁師や業界関係者とのネットワークを構築し、最新の情報や技術を共有する
- 資格の取得: 高度な船舶操作資格や、海洋生物に関する資格を取得することで、より高い評価が得られる
漁師になるための情報を得るには、以下のウェブサイトが役立ちます
- 日本水産庁: 漁業関連の法律、規制、支援策についての情報が満載
- 漁業協同組合連合会(全漁連): 各地の漁業協同組合の連絡先や支援プログラムについての情報を提供している
- Hello Fisher: 漁師専門の求人情報や業界のニュースを提供するサイト
これらのサイトは、漁業に関する最新の情報を提供しており、漁師を目指す人々にとって非常に有益です。
まとめ
未経験から漁師になる為には、多くの情報と準備が必要ですが、適切なアプローチで実現可能です。以下にその要点をまとめます。
- 漁師の仕事は体力的、精神的に要求が大きい
- 適切な教育を受けて、必要な資格を取得する
- 実際に体験して経験を積む
- 地域の漁協と良好な関係を築く
- 最新情報は専門の情報サイトで確認する
漁師という職業はただの仕事ではなく、自然と向き合うライフスタイルの一部です。
適切な教育と準備を行い、漁業界に新たな一歩を踏み出しましょう。


